「ダンジョン飯の絵柄の移り変わり」←に対するみんなの反応集【ダンジョン飯】
[音楽] 今回はダンジョン飯の雰囲気に対する皆様 の反応を紹介します皆様からのコメント高 評価お待ちしています初期と後期でだいぶ 違うよね序盤は淡々と静かに進む感じだ けど後半はも雰囲気もすごい賑やかになっ た初期と後期でっっていうとマルシルの 扱い思い出すあいつ初期の上の階層だと あんまり強そうに見えないけど下の階層 行けば行くほど有能差が目立ってくる マルシルの扱いの変化はダンジョン飯の ストーリーの肝だよね物語のテーマに沿っ て情報が少しずつ開示されていって中心 人物として等角を表してくの本当やり方う と思ったわキャグのキれも後半になるに 連れてましていった初期マルシや チルチャックがよく言われてるけど ライオスも初期と終盤で結構顔が変わっ てるよねあと戦士の初登場シーンがやべえ やつすぎる10年近くやってればそりゃ 多少は変わるでしょなりは髪が短くなって エロくなったよななりは後半になって腕の むっちり具合がましたのもエロいとスケベ なめで見ているマルシルの泣き顔から摂取 できるビタミン汚くなってるまあギャグ 泣きとマジなきだから改めて原作読んだ けどプシフターの買当たりからキャラの 書き分けが変わってきたような気がする 漫画は連載進むに従って映が陥落化される パターンもあるけどダンジョン飯は ディテールの書き込みも増えて作者の力が ぐんぐん上がってるのが感じられたな最初 からうまかったけど途中からめっちゃうく なってる骨格フェチ感がすごい初期は一見 ほのぼの見える中にうっすらと不安感が 漂う編の空気感残ってる話も短編が何度も 乗ってる感じ話が進むに連れよさを残し つつ連載ものらしくなった最初は正直 あんまり絵がうまいとは思わなかったけど 途中から力が天元突破していったデ取りと か読んでると休憩でを描くタイプらしく まあそりゃがよく上がりますよねとあと 好きなことは徹底的に調べるタイプっぽい よねこういうところも作品に反映されてる と思う 初期作品とか昔の落書き見ると元々時間 かけてうまい絵を描くタイプだったのが 初めての連載でペース配分になれなくて ぎこちなくなってたんかなと思うその辺 慣れてきたことで本来のうさや魅力が出て きたのが後半って感じぎこちなくなってた とかじゃなくて序盤はコメディ乗り似合う ように書き込み少なく単純化して書いてた んだと思う過去の作品を見てもシリアス ファンタジーを繊細で緻密苗で描いてる 反面ギャグ4コマ漫画では簡単作画と絵柄 を使い分けてる絵は最初からうかったけど いかにもオリジナル創作同人上がりの細く て均一な線でべた塗りが少ない白っぽい 画面から線の強弱で立体感を出しつつベタ やトンでくっきりノタを作る商量漫画 っぽい味やいが作りになったコカトリス見 た時う って言っちゃったわ迫力やべえよ鳥と爬虫 類あと魚のリアルな正面顔ってすごい 難しいのにねとても勉強になるその後の 展開を思い出して笑ってしまうやろ初期は ロクトフェイとしてからの死体回収蘇生 っていうあるあるネタみたいな話だったな だんだん状況がれにならなくなるにつれて 絵柄もそれに合わせてった 感じ間読んだ時点ではまさかこんな見開き が出る漫画とは思わなかったよなこれ祭式 ばっちりやれば本格的な絵画にしても普通 に成立するよね教会とかに置いてたら宗教 画として認識するかもしれない絵だと思う エロいよななんかせへの欲動というか現象 のリドを感じる個人的にはと目を奪われた のはそのシーンとその少し前のダンジョン 内の乱状態の際に翌自子が巨大な姿を人々 の前に表した見開き絵がうまいだけじゃ なくて視線友道だの白黒のノタだの漫画と いう読み物としての演出とか漫画力とか いうのそういうのも東大の漫画家の中でも 本当のトップクラスの上積だと思うあと 世界観とかキャラクター背景とかそういう 設定ニコル作家は他にもたくさんいるの だろうけどダンジョン飯では物語の進め方 とかドラマ場面の演出で本当に自然に うまく設定が矛盾なく一貫性を持って機能 してるしそれがここまでできる作家は そういないんじゃないだろうかそういう 意味でも世間的にもっともっと評価されて 欲しいこの作者マジでがうまいので連載の 慣れや上達もあるだろうが短編集の頃から 短編の雰囲気に合わせて書き込みや書き方 をしっかり変えてるので計算も生まれてる と思うんだよな作品の雰囲気を作者自身が 掴んで適合させてるっぽいのは連載の賜物 と上達にも含まれると思うが1巻ないや2 巻まででもだいぶ絵が変わってるから上達 もあるだろうけど単とした雰囲気の作品で いくか波のあるドラマの作品でいくか初期 は模索してて校舎に決まったからそれに 合わせたのもあるんじゃないかなこの ディフォルメ本当好きいい意味で最初の 雰囲気から裏切られるよねあるあるギャグ 漫画から臨場感たっぷりの冒険もへの変貌 感というか画から漫画になった感じはある 一巻からうまかったけどどんどん線が太く 画面が濃くなっててビビる書き込みが 増えるのはハルタさかあるあるだよね 書き込みやばいはずなのにどうして読み やすいのか視線誘導とかがうまいのかな シンプルな小回りや視線誘導もいいが やっぱり白黒のバランスの取り方がいいん だと思うあとキャラが小さく映ってるコで も表情が分かりやすく見えるデフォルメ 具合とかも序盤はコミカルな冒険料理が 中心で後半は世界の名運をかけた悪魔討伐 だから画風の変化で単純な力の向上とも いいきれんと思うわ元から相当うまいと 感じるいやそれでもやっぱもっとうまく なってるか個人的にしびれたのは最後の ファリンが夢のの中で食べ物を消化する シーンだなモンスター積極的にかける時点 で漫画家としては上積みレベルだけどね 元々なんで上積がさらに進化してんですか 第1部と第2部で雰囲気がからっと変わる のは意図した演出だと思う第1部では妹を ドラゴンから助けないとという焦りはあっ たもののまだ時間の猶もあると思われてた し比較的まだ緩めの雰囲気で進んでたけど 終盤になるとタイファリゴンカレーといい 重要なシーンはあるが全体的に戦士の料理 シーンが少なくなるのがちょっと寂しかっ たっけな例のレッドドラゴンも何気に初 登場時の顔がだいぶ別人というか最登場 以降の鱗の書き込みと重厚感がえぐすぎる 多分そこら辺の絵描きとか漫画家ならよ 自子の全身図けって言われた時点で泣くぞ 決の絵は綺麗でかっこよくてデフォルメの 絵は可愛くて面白いから好きがないやばい 魔法陣がしするに見つかったとこで雰囲気 が変わったと思うあそこまではファリンが 生き返ってまだ続くのって感じだった序盤 終盤で雰囲気が大きく変わるんだけど テーマのブレを一切感じないのはすごい どっちかというと魔物色が想像以上に うまくいって体調管理もばっちりだったの で後半は割とバンバンマルシルの魔法に 頼れた感じ 最初の方は言うなれば純度の高い漫画へ だった連載が続くにつれて今風のアニメ的 なフレーバーが転化された気がする一言で 表現するなら手慣れたってことか も最後までご視聴ありがとうございます ダンジョン飯の雰囲気への皆様のコメント お待ちしていますチャンネル登録も よろしくお願いします
ご視聴ありがとうございます!
第2期制作決定!の「ダンジョン飯」で話題の反応動画を制作していきますチャンネル登録・高評価宜しくお願いします!
https://amzn.to/3vhQ91a
↑ダンジョン飯シリーズ 九井 諒子 (著)
https://amzn.to/43nawqe
↑ダンジョン飯 ワールドガイド 冒険者バイブル 完全版 (HARTA COMIX)
https://amzn.to/43lTf0N
↑九井諒子ラクガキ本 デイドリーム・アワー (HARTA COMIX)
https://amzn.to/4amLw5t
↑ダンジョン飯 Blu-ray BOX
※本件はAmazonアソシエイト・プログラムに参加してご紹介しております
・著作権に関しまして
動画で掲載している画像などの著作権や肖像権等は全てその権利所有者様に帰属致します。
各権利所有者様や第三者に不利益がない様配慮しておりますが、動画の内容に問題がある場合は、各権利所有者様本人からご連絡頂けましたら幸いです。
引用元
https://bbs.animanch.com/board/3495417/
出典
©九井諒子・KADOKAWA刊/「ダンジョン飯」製作委員会
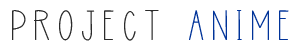
7件のコメント
もともと画力はすごくて、短編で色々書き込み具合を作風によって変えてたんよね
しかもそれぞれが破綻なく上手いという・・・
ドラゴン戦あたりから絵柄を一気に重くしたのは雑誌とかが作者にインタビューしてみて欲しいところ
元々うまいけど、画力も構成力も序盤と後半では桁違いにあがったとおもう。作画がはっきり変わったのは炎竜戦からかな。わりと説明的だったアクションシーンに力点を置くようになった。
初期はアナログ作画だったみたいで(線画だけかフルかはわからない)すさまじく密度が上がったのはデジタルに移行したんじゃないかな…?あのレベルの月刊連載をアナログでやってたらアシスタントさんいても手が壊れそう。アナログで鬼密度作画、森薫先生みたいな例外もいるけど…
元々絵が上手い人が連載のために簡単作画をやってたが、連載を続けるうちに早く書けるようになり、本来の絵で作画するようになった感じ
初期は極力戦闘シーンの描写を避けるようにしてた印象だけど、後半はちゃんと魔物や人間の戦闘シーンを多角的に書けるようになってたような気がする。
どこかで「途中からストーリー漫画にするように方針を変えた」という仮説を読んだけど、自分はそうは思わない。
キレイに回収された第1話からの伏線をみるに、また、ファリンを救出しかけて失敗し最後の最後に大団円で成功するという
読者を一行に対する同情心に誘い込む構成のち密さ・見事さから察するに、・・・最初からこういう物語にすることは、決めていたと思う。
ただ、これがどういうテイストのマンガになるのか(ギャグなのかシリアスなのか)、描き進めてみるまで探り探りだったんだと思う。
後半は話の展開が早くてなかなか飯が出なくて残念だった、そこに郷土料理二郎系で糞ほど笑った
寓話的な簡略な描線のキャラクターで始めたけど。
やっぱり書き込みたくなるんだろうね。
久しぶりに初期の短編ものも読み直して見たが。
一段と味わい深く思えました。